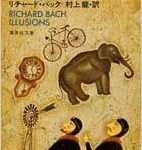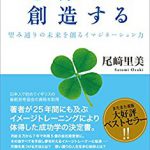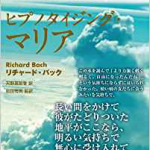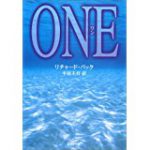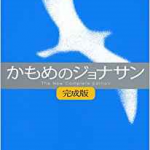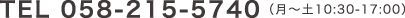「生命を護り、育む家。」二回目のテーマは光、です。
聖書は冒頭で「光あれ!」と神が言ったことからすべてが始まります。
ドイツの文豪ゲーテはもっと光を、と言いながら死んだと伝えられています。
当たり前ですが人間は光がなくては生きられないし、存在し得なかったわけです。
SUN GAZING(光を見つめる)という健康法に関する60ページのレポートによると、日昇あるいは日没前5分間の太陽光を見つめることで何年も不食(最低限度の栄養吸収で生活すること)を実践している人がいるそうです。(様々な事前準備の上でのことですから単純にマネしないでくださいね)
光の重要性については、私たちの日常生活で十分に感じるところですが、どうして大切なのか、ということに関する明確なエヴィデンスは以下のとおりです。
第一に、THE UV ADVANTAGE (MICHAEL F.HOLOCK PH.D.,MD著)という本によれば、太陽光によるメリットの一つにヴィタミンD3の生成があります。ヴィタミンDが不足すると骨粗鬆症、クル病、鬱、癌などさまざまな障害を引き起こすことが指摘されています。
第二に、DAYLGHIT IN SCHOOLSという130ページのレポートによれば、1999年にアメリカでTHE PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY社が実施した太陽光(あるいは太陽光に近い波長を出している照明)に関する影響を調べた実験データがあります。
この実験により、太陽光(あるいはそれに近い照明)のもとで学習した生徒は、そうではない照明の下で学習した生徒とよりもよい成績をとれた、という明確な差が出たことが証明されています。
いかに光を取り入れることが重要か、というわけですが、一方で、残念ながら大気汚染によるオゾン層の破壊で、人間にとって有害な紫外線(UVA)が天空日射に大量放射されているため、気持ちの良い日でもある程度遮光しないと身体へのダメージがかかってしまいます。
なくてはならない光が身体への脅威になる。それほどまでに光の力は大きいとも言えます。
何事もバランスですね。
最近では、紫外線予報もある程度出されるようになってきたので、光との接触レベルをコントロールしやすくなりました。
では、そのような光をどう家に取り込むか?(採光といいます)
新築やリノベーションで窓の位置やサイズを考える場合、参考にしていただきたいのが、以下の3点です。
①北面は年間通じて安定した採光が期待できる。
②天窓は通常の南面採光の約4倍の光を取り入れることが可能である。
③壁面の高い位置に最高を設けることでプライバシーを守りながら光量を増やすことができる。
住宅では南面に大きな窓をつけたい!という要望が一般的に多いですが、実は日本では南面は採光量が安定しづらい、という事実があることをご存知でしょうか?
太陽の動き(もちろん実際には地球が動いてるんですが)は一年を通じて変化します。
春・秋はより北東から日が昇り、やや低めにより北西へと沈みます。
夏場は高度もたかくなるため、庇(ひさし)の長さによっては、採光できなかったりします。
これらに関してどのように設計するのが理想的か、というと、時間が許されるなら、一年を通じて太陽の動きを観察してから設計に入ればよいと思います。思い違いや後悔を圧倒的に減らす効果的な手段ですし、実際にそういうレベルで建てられたクライアントの家もあります。
そこまでの時間的余裕がない場合は、設計レベルでシミュレーションするのが一つです。フルハウスでもCADソフトを使ってある程度はパースから予測できます。
光が時に囁くように、時に包み込むようにある時間や空間を、イメージするだけでもなんだかとても満たされた気分になります。
太陽の動きやさまざまなすまいの条件を考えながら、さまざまな方法で光を取り入れたあなたやあなたのファミリーの生活はどのようなものでしょうか?
それらを考えたり、ワクワクしたりしてイメージしていくことが理想のライフスタイルを決めていくプロセスとなり、それらがより力強く実現されていく方向へと向かっていくのです。
次回は「水」をテーマに考えてみましょう!